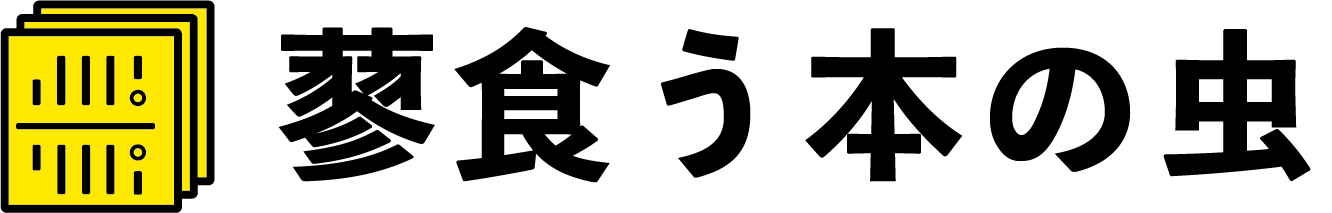私が森瑤子さんの文章に出会ったのは大好きな小説の文庫の解説だった。
読者のみなさんは文庫で小説を読むとき、解説から読むだろうか。私は、たとえばミステリーであればそれだけで犯人やトリックが分かってしまう場合もあるし、その他のでも内容がわかってしまうことがあるため、絶対に先に読まない。解説は食後のデザートのようなもので、余韻を楽しみ、作品や著者への深い理解を促すものと私はとらえている(残念ながら、いかにも頼まれて書きましたというおざなりな解説も多いが)。そして好きな作品がハードカバーから文庫になったときの、解説者のチェックも欠かさない。良い解説者は読んだ小説の読後を邪魔せず、かぐわしい小説の残り香を楽しませてくれる。
森瑤子さんの解説は小説の愛に満ちていて、私のなかで最高の「文庫本小説の解説」を書いた。いまさっき読み終わった読者とともに興奮を共にしたい、という情熱にも満ちていた。
始まりは肉体である。そしてなりゆきは心である、という言葉について、もう一度考えてみよう。けだし名言である大げさでも何でもなく今世紀最高の名言だ。ふざけているわけでもない。歴史に記されるべき名言だ。私は大真面目でそう思っている
(山田詠美『熱帯安楽椅子』p170 集英社文庫)
本当は全文引用したいと思うが、ぜひ文庫本をチェックしてもらいたい。『熱帯安楽椅子』の森瑤子さんの解説は、とても情熱的である。
私は大好きな『熱帯安楽椅子』を的確に、かつ鋭く、森瑤子さんと共に語り合っているような錯覚に陥った。そうそう、これが言いたかったの、と。しかし私が森瑤子さんの文章を読み始めたときには、彼女はもう亡くなっていた。
森瑤子さん、と名前を聞いても最近は彼女の偉業どころか、名前すら、伝わらない・知らない場合も増えてきた。まったくもって文化的な損失だと私は思う。ぜひ森瑤子さんのことを知って欲しいと思い、まず彼女のプロフィールから紹介したい。
- 1940年11月、静岡伊東市生まれ。東京藝術大学器楽科(ヴァイオリン専攻)卒業。
- 大学卒業後、広告会社に勤務し、英国人と結婚。三女の母になる。
- 1978年、38歳で「情事」で第二回すばる文学賞を受賞し、デビュー。
- 「誘惑」「傷」で芥川賞候補、『熱い風』『風物語』で直木賞候補にあがる。
- 1993年7月6日、胃癌のため52歳で逝去。
驚くべきは25年という執筆活動期間のなかで、著作は100冊(!)を超えていることだ。しかもいくらカンヅメ(ホテルの部屋や編集社の一室を使って、朝から晩まで原稿のことを考え続け、執筆すること)をしても、夕方6時には必ず家に帰って夕食の支度をするという、見事な兼業主婦としても有名だったらしい。
今でこそ兼業主婦女性は多いが、森瑤子さんの活動されていた時期はちょうどバブル世代で、専業主婦が多かった。物質的にも経済的にも上向いていた時代だが、同時に現代的な女性の問題が浮上してきた時期でもある。
娘であり、母であり、妻であり、女であること。その当時、物質的には恵まれているが、自立した女性になれないということに悩んだ主婦の方たちが多かったのは想像に難くない。森瑤子さんはそんな「悩める自立をしたい主婦」の代表だった。森さん自身も夫や娘との関係に悩んだ。『叫ぶ私』(1985年)という本は森さん自身のセラピー(今でいうカウンセリング)を受けていた模様を一部、本にしたものだ。家庭というなかで、「働く私」がどこに位置づけられるかの悩みが克明に描かれている。この問題は日本においてまだ解決されていないし、個人的な問題とされている。しかし今も多くのワーキング・マザーが抱える「私はこのまま歳を取ってもいいのか」という問いに真摯に答えた人物として森瑤子さんの名前をあげるべきだ、と考えている。
森瑤子さんのデビュー作「情事」(1987年)で起きることは婚外恋愛、つまり「不倫」である。「不倫」と聞いて嫌悪感を催すひともいるだろう。今しばらくお付き合い頂きたい。いまでこそ自らのセクシュアリティをネットや本を通して容易に語れる時代になったが、70年代後半から80年代は女性の婚期は「クリスマス・ケーキ」にたとえられていた。つまり25歳を過ぎると結婚市場で「叩き売られる」人生にあったのだ。いまでは考えられない時代錯誤な考え方だ。じゅうぶんな性愛の知識もなく、結婚をして、子どもを生んで、セックスライフはそこで終わってしまう。24歳で結婚し、子どもが小学生に上がるころ、30代半ば。女ざかりの季節なのに、夫からは性的魅力の対象外として扱われ(妻もまた同様に夫に性的魅力を感じない)、インテリジェンスはあるが、会社で働いているわけではないから社会的地位もない。そんな八方塞がりのなかで社会の窓口のメタファーとしての「不倫」小説を森さんは多く書いてきた。
夏が、終わろうとしていた
(『情事』p11 集英社e文庫)
この一文には季節的な夏と、女性としての人生――恋愛をし、結婚をし、子どもを生んだ女性の生き方の――「夏の終わり」つまり、ミドル・エイジ・クライシスが起こっていることを示唆している。
家の中には既に、濃い倦怠に似た夕闇があった。私は、わずかの間、その陰の中に、ひっそりと佇んでいた。
あのように、極く自然に後ろめたさを演技し、冷めた心を巧みに羽撃かせ微笑に変えて夫を送り出したことが、厭らしい、安っぽい演技じみたやり方のように思い返され、それに対する夫の、これまた、作為的な無関心さの中に、私たち夫婦の、牙をみせあわさないですまそうとする共犯意識があった。それは私たちは、もう習慣のようにしてしまっていたが、それまでまだ魂の何処か深い襞の陰で、不満や怒りに似たものが、拭い切れない焦燥となって燻り続けていた。(『情事』p53~54)
主人公のヨーコは上記のように述懐する。
そして夫との関係も冷めて、「なんとなくこのまま歳をとってしまっていいものか」という不安がヨーコに表れている。そして六本木の外国人が集まるバーでレインと出会う、レインと出会うことによって、ヨーコは性的に満たされることとなる。しかし……。
この場合、レインはアメリカ国籍の35歳、独身だ。レインが外国人であることは、大きな問題ではない。「女性」作家が外国人を書く場合、それは「ここではない、どこかに連れて行ってくれる」存在のメタファとして描かれる(山田詠美さん然り)。
この先は中編小説『情事』を読んでぜひ確認していただければと思う。
森瑤子さんの著書は100冊を超える(私は70冊くらいしか読んでいない)が、また短編の名手であることも知られている。私の大好きな短編集『垂直の街』(1990年)の中にある短編を紹介したいと思う。「タクシードライバー」という短編だ。
主人公のバーニー・コワルスキーはニューヨークに住む男性のタクシードライバーだ。郊外にラブラドールの子犬をもらいに、タクシーを走らせる。亡き妻のエズメの空白を埋めるため、子犬を飼おうと決心したのだ。ニューヨークに雨のなか帰るため、子犬のブルースと共にタクシーを走らせていると、ある女性を思いがけず拾うことになる……。
バーニーは亡くなったエズメを想いながらタクシーを走らせているとき、泣いてしまう。
もう二度とエズメには逢えないのだという思いでバーニーの胸がしめつけられる。再び視界が不透明になり、ワイパーのスイッチを強にするが、それはすでに動いており、不透明になったのは、雨のせいではなく自分の涙だと思い知らされる。
(『垂直の街』p109 集英社文庫)
妻を失った男性の孤独。それは私には想像がつかないが、ふいに涙があふれてしまう瞬間があると思う。愛しいひとを思って涙を流したり、大切なひとを失ったことを後悔して泣いたりすることは誰にでも経験があると思う。そして泣いていることにすら気づかず、鏡を見ると、窓に反射する自分の顔を見ると、泣いている、ということ。
バーニーは妻を失ったという喪失に、耐えられない。それは性別を超えて、普遍的なことだと私は思う。
「タクシードライバー」は大きなどんでん返しがある。これ以上、語ってしまうとネタバレしてしまいそうなので、ぜひ本を手に取ってこの短編小説の行く末を読んでみて欲しい。
森瑤子さんはエッセイも多く書かれている。そのなかで紹介したいのは『夜のチョコレート』(1990年)というエッセイだ。このエッセイは20代の女性――独身女性や結婚まで働く女性について――の恋愛や生活の、些細なことについて品格が表れると指摘している本だ。夜のチョコレートは大人の女性の特権である。それが似合う女性とはどういう人間か、ということについて子細に書かれている。
だから美しい言葉を正しく使えば、知らず知らずのうちに、優美で美しいひとになれるものだし、反対に崩れてだらしのない言葉を使い続ければ、やっぱり崩れて見た目もだらしのない女になってしまうのだと思う。
(『夜のチョコレート』p13 角川文庫)
このたった6ページの「大人の女になるための言葉美人のススメ」はエッセイの最初に書かれている。作家としての森瑤子さんの意識が、このエッセイに表れている。ボキャブラリーが少ない女性を九官鳥だ、と鋭く指摘している。会話を楽しむために、「私について」話すことではなく、相手の意見を聞きなくことが重要だ、とスカッとした文章で書いている。そうすることで、知性をじゅうぶんに発揮できると、森瑤子さんは指摘している。
私は30代だが、「煙草の吸い方」や「長電話の女」、「たまにはタブーを無視しよう」、「言葉ブスは顔もブス」などなど、彼女からのメッセージをいまでも参考にしている。まだまだ森さんの言葉から学ぶことも多く、何度もこの『夜のチョコレート』を読み返している。まったく頭があがらない。そして日々の反省をする。
森瑤子さんの美学は「自分で決める・自分で責任をとる」というシンプルなものだ。しかし自分で決めて、その責任を負うことはなかなか難しい。しかし森瑤子さんの小説の登場人物は、誰かのせいにしたり、何かの物事のせいにはしない。エッセイでは自分で決めて、自分で考える力のつけ方をおしえてくれる。限られた生活のなかで、自分で選びとる力を養わせる作品たちばかりだ。森さんの作品を読むたび、私は襟を正す。泣いても、笑っても人生は一回きり。それならば森さんの小説に倣って、私は「ハンサム・ウーマン」になりたい、と思っている。