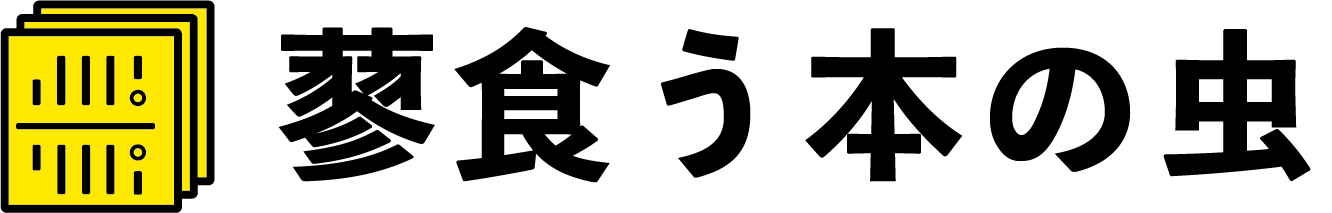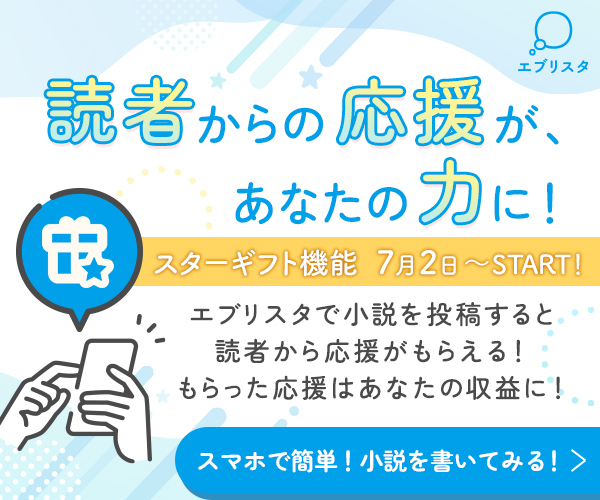この記事の目次
アマチュア小説家は経済的自由の夢を見るか?
私たちは小説を書くとき、どこか出版社や文学賞を意識していないだろうか。デビューするために。名声を得るために。お金を得るために。
もちろん、自分のオリジナリティを前面に出した小説を書いている人もいるだろう。でもそれは、人の目には留まりづらい。なぜなら出版社から出版されていないからだ。小説投稿サイトで有名にもなっていないからだ。
私は、小説は「自分のオリジナリティを最大限に表現してこそ」だと思っている。そうしてそういった「極めて個人的で独自性の強い小説」にスポットライトが当たらない、今の仕組みが問題だと思っている。
特に、純文学といったジャンル(あえてここではそう表現する)なんかが顕著だ。注目もされず、もちろん収入も生まれず、孤独で、内的世界を処理するだけ。
もうそんな「作家は食わねど高楊枝」みたいな生き方、ごめんだと思いませんか?
クリエイターにとっての理想郷「トークンエコノミー」
あなたは「トークンエコノミー」という言葉をご存じだろうか。
「トークン」は「代替通貨(日本円やドルに代わるもの、証券など)」という意味。エコノミーは経済だ。
簡単に言えば、仮想通貨を使って「株を発行できる」といったものだ。「トークンエコノミー」は作家やクリエイターにとっての一つの理想郷だと私は考えている。
なぜ理想郷なのか? 私たちはそこで「極めて個人的な作品を創りながら、収入を得ることができる」からだ。具体的に言うと「アマチュア小説家が自分の株を発行すればいい」と考えている。
(※ちなみに、ここで言う小説は「webで公開していること」を想定している。)
具体的な流れ
例えば私がトークン(株と思って可)を発行したとする。1000トークン発行したとしよう。
これを誰かが1トークン100円で100個買ってくれたとしたら、100×100で10000円になる。
- トークン発行
- 誰かがそれを買う
- 発行者に利益が発生する
寄付と何が違うの?
ここまでは寄付のような善意で行われる一方的な関係に見えるかもしれない。
しかしトークンエコノミーは購入者にもメリットがある。それは購入者したトークン(株)に値上がりが期待できる、というところだ。
- 購入者は買ったトークンの価値を高めるためにクリエイターの小説を「宣伝」する。
- クリエイターやその小説に注目が集まりトークンの価値が上がる。100円が120円になる。
- 20×100で2000円利益が生まれる。
作家のメリット
次にメリットを整理してみよう。
- トークンにより従来よりも簡単に小説からの収入が期待できる。
- 作品の注目度が高まる。
さらに①と②はサイクルする関係だ。
トークンの価値が上がる➡注目度が高まる➡注目度が高まってさらに価値が上がる➡繰り返し…。
読者のメリット
- 有望なweb小説のトークンを持っていれば、その作品が有名になったとき、値上がりが期待できる。
- 誤字訂正や宣伝、レビューの対価にトークンを貰える。
私は特に②がさらに活発になることを期待している。
現在、小説界隈にいるスコッパーは大体が有志だ。ブログのネタになるかもしれないが、微々たるもの。誤字訂正なんて本当にその作品が好きでなければやらないだろう。しかし、上記のように今まで無償だった宣伝やレビューに対価期待できるようになればモチベーションも上がるし、より良質なコンテンツが広まっていくだろう。
デメリット
もちろんデメリットもある。
- 利益に対する税のかかり方がややこしい。
- インサイダー取引の横行
- 詐欺の横行
①②③は仮想通貨界隈、全体に言えることだ。
①の仮想通貨で得た利益は雑所得で処理されるが、まだまだ分かりにくい。
②③はトークンをエコノミーが活発になればなるほど発生するだろう。
トークンエコノミーの具体例
そうは言っても、トークンエコノミーなんてよく分からない。実際、どんな仕組みで動くのだろう、という方のために以下の具体的なサービスを紹介する。
①VALU
VALUは個人の価値を疑似株式のようにして売りに出せるサービスだ。
昨年、かなり話題となった。SNSのフォロワー人数などからVAを計算するだけで、個人の時価総額が算出される。
例えばフォロワー10000人のAさんの価値は1000万円、みたいにだ。
これを1VA何千円、等に分割して売りに出す。このVAは株式のようなもので、価値の源泉は簡単に言えば「この個人がもっと有名になるか」なので、有名になれば価格が上がる。そして、有望そうな個人にはたくさんの買い注文が入り、お金が簡単に集まるといった仕組みだ。
ちなみにこのVAを保持しているからといって、必ずしも優待を受けられるわけではないし、値上がりが保証されるわけでもない。あくまでもファンとしてお布施するくらいの気持ちでやった方が後悔も少ないだろう。
このVALUは仮想通貨を知らない人たちに、初めて分かりやすい形でその破壊的イノベーションを見せつけたケースだった。なのでもちろ混乱も生まれた。インサイダー取引や詐欺が横行したのだ。某有名ユーチューバーがホルダーに内緒で突然、大量のVAを売りに出した事件(大量の価値が売りに出されると当然価値は下がる。ホルダーのVAの価値も下がってしまう。ホルダーはもちろん怒り心頭だ)は記憶に新しい。
VALUは個人を疑似的な株式会社とすることで、より細かいお金の流れを産み出したサービスと言える。
②ペペキャッシュ
あなたはトレーディングカードをやったことがあるだろうか。遊☆戯☆王とかマジックザギャザリングとか。似たような仕組みがトークンエコノミーにもある。それがペペキャッシュだ。
ペペキャッシュはブロックチェーン上にイラストを保存することができる。それはつまり、一枚しか作られなかったら必ず一枚しか存在しない、オンリーワンのカードが生まれるのだ。そしてカード毎に価格が決められていて、ユーザーはそれをやり取りできる。発行枚数の少ないカードはレアペペと言われ、希少価値が高い。
ペペキャッシュはVALUより比較的健全で混乱の少ないコミュニティだ。仮想通貨界の有名人たちも、ペペキャッシュをやっていることが少なくない。
これこそ分かりやすいトークンエコノミーなのではないだろうか。上手で魅力的な絵は高値で取引され、クリエイターの利益にもなる。そしてクリエイター自身がVALUなどで、個人としての価値を売りに出すこともできる。トークンエコノミーの循環だ。
まとめ:ネット小説家が「トークンエコノミー」を持つ意味
自分だけの、文字通り「世界」を持つことができる。
そこには、自分がいて、ファンがいて、独自の通貨がある。ファンがレビューをしてくれたり、小説を買ってくれたり、宣伝してくれたりすれば、その独自通貨を送る。
そうしてコミュニティが盛り上がっていけば、独自通貨は流通量が増え、時価総額も増える。時価総額が増えたなら新たなファンも呼び込めるし、保有している人の資産は増える。プロもアマチュアも関係なくなり、「作家⇔出版社⇔読者」、という金の流れの図式が「作家⇔読者」に書き換わる。
もちろん出版社が無くなればいいとは思っていないし、残り続けるだろう。でも、中間のメディアを介さずに価値のやり取りができるなら、それは一考するに値すると思う。