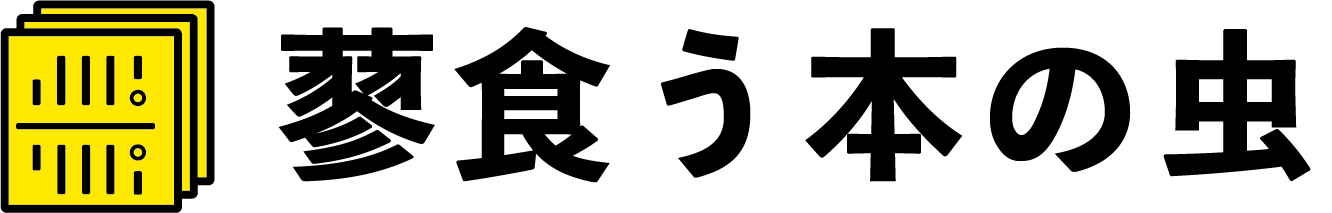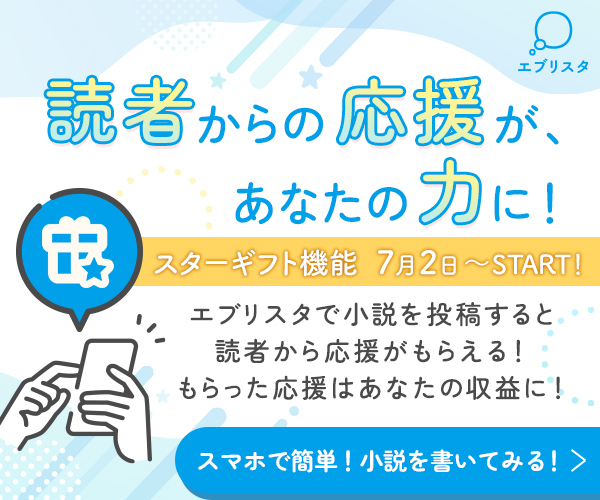今回の記事は強い言葉での表現や考え方が色濃く出ているため「こういう考え方もあるんだ」という見方で読んでいただけたら幸いです。
私は前回執筆した記事の通り、学生時代に出会った当時の教授であった詩人・高柳誠さんから文章表現の基礎を教わってきました。
しかし、その一方で創作全体に関わる姿勢にも積極的に触れることが出来ました。
今回は高柳さんの創作観について書き記していきます。
この記事の目次
「感性を枯らしてはいけない」 / 高柳流(?)感性の鍛え方。
授業中に時折、高柳さんが話していた話題がありました。
10代、20代と若くして才能に溢れていた作家が、30代になって以降の作品がぱっとしなくなる、という旨の発言が多く出ていました。
高柳さん曰く、身体と同様に思考も衰えていくことに気づかないまま、感性だけで作品を作ってしまうとこういった作品への行き詰まりに直面してしまうようです。
そして、高柳さんは感性を枯らさないための方法として、2通りの鍛え方を教えていただきました。
ひとつは「作品を作り続けること」で、脳も筋肉と同様に使わなければ衰えてしまうため、創作を続けるだけでも感性を衰えにくくすることができます。
もうひとつは「異なる分野に触れること」です。文章表現の分野だけでなく、美術館、映画、コンサートといった他のアートに触れることで新しい表現方法を養うことができ、作品の幅を広げることが可能となるでしょう。
「問題作を作りなさい」/ 高柳さんの発した「問題作」の意図とは。
私の中では、文章表現の授業で一番驚いた発言かもしれません。
高柳さんは学生の皆さんへ、文章を書くなら尖った作品を作ってほしいと話していました。
レビューサイトで星5つの作品よりも問題作と言われるような星3つの作品を読み、執筆した方がいいと、高柳さんは考えているようです。
レビューで繰り広げられる問題作のなかには、裏を返せばそれだけ読者それぞれの解釈を生み出すことのできる作品でもあるため「自分だったらどう解釈するか?」と考えながら作品を読み、色々な見方のできる文章で表現することを勧められました。
「作品を書けなくなった時期があった」/ スランプに陥り、そこから脱した時のエピソード
長年執筆し、本を出版してきた高柳さんもスランプに陥ることがあったそうです。
何を書いても自分の文章に見えず、嘘を書いているような感覚が続いていたとのことでした。
では、どのようにして高柳さんはスランプから脱却できたのでしょうか。
悩んでいた当時の高柳さんは、ある考えにたどり着きます。
それは「『言葉』というものは、長い歴史を生き続けている巨大な生き物の力を借りることなのだ」という考えに至り、それに従って再び文章を書くことができるようになったと仰っていました。
言葉を神聖な生き物の力として解釈してこそ、必然的に選ぶ言葉に迷いが消えていったそうです。
まとめ「作者の伝えたいことなんて全部わかるわけがない」/ 高柳さんの考える「良い作品」とは
これは学校等で国語のテストに出てくる問題「作者の伝えたいことは何か?」について話題が出た時の高柳さんの言葉です。
高柳さんが考える優れた作品とは「読んだ読者の数だけ異なる解釈ができる作品」とのことでした。
これは高柳さんの経験上「作者が本当に伝えたいことは読者には半分ほどしか伝わらない」と仰っており、作品のすべてが伝わらないからこそ自由に物語を描き、読者が様々な捉え方ができる作品こそ優れているのだと度々力説されていました。
冒頭にも書き記しましたが、詩人・高柳誠の創作の姿勢を書くにあたり、これが必ずしも正解とは限りません。
「こういう捉え方があるんだ」という解釈で、皆様の創作活動に少しでも役立つことができたなら幸いです。