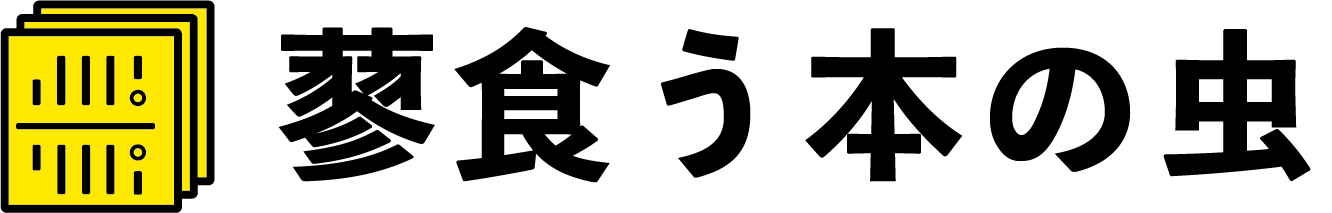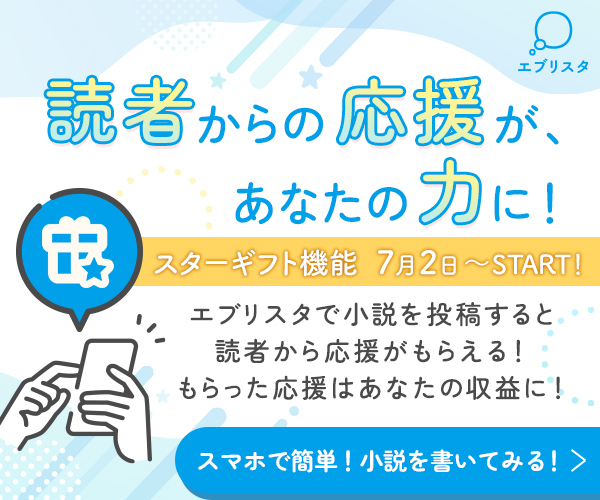「5・7・5・7・7」による31音の言葉の並びで、情景や心情を表現する短歌。その短さが気軽さとして魅力的でもあります、一方でこの短さが読み解きにくさの一因でもあります。
「なんだかよくわからないな」と、そのまま読み進めるのももちろん読者の自由。でも「もしかしてこういうことが言いたいのかな?」と作品に迫れることができる、ちょっとしたコツを紹介していきます。
表現技法(レトリック)とは
冒頭で触れたように、短歌を読んで「これは何を言いたいんだろう」と考えることは、さほど珍しいことではありません。限られた字数の中で、すべてを完全に言い尽くすのはやはり難しいことです。
そんなとき注目したいのが、一般に「レトリック」と呼ばれる表現の技術。以下では、みなさんにもお馴染みであろう「交通安全標語」を取り上げ、実は日常で身近なレトリックをピックアップしてみましょう。
なおここで取り上げる標語は、一般財団法人全日本交通安全協会および毎日新聞社主催の「交通安全年間スローガン」より引用します。
具体的なレトリック
レトリックと一口に言っても、細かく見ていくと様々な表現があることがわかります。ここでは代表的なものをいくつか紹介していきます。
体言止め
暗い道 私のお守り 反射材
標語なので意味は一読して明白だと思うのですが、一応解説すると、「暗い道では私のお守りとなるのが反射材です」ですね。
この短いセンテンスのなかで使われているのは「体言止め」。体言止めとは簡単にいうと「物の名前(名詞)」で、文章を終わらせることです。普通の文章であれば、「反射材です」となりますが、ここでは「反射材」と止めることにより、反射材が強調される効果があります。
助詞の省略
暗い道 私のお守り 反射材
実はさきほどの標語には、ほかにも表現技法があるのです。
細かいところなので意外と気づかないかもしれません。よく見ると日本語でよく使われている“あるもの”がないのです。
ここで使われているのは「助詞の省略」。いわゆるレトリックとは少しことなりますが、短歌ではしばしば助詞を省略して表現することがあります。
上の標語に助詞を補うと「暗い道“での”私のお守り“は”反射材」となります。
助詞は文章のニュアンスを左右するので、非常に重要な役割があります。短歌の読解のしにくさの一つが、助詞の省略ともいえますが、ここを自発的に補えるようになると、ぐっと作品内容に迫れるようになるといえるでしょう。
倒置法・対句
よくみせて ちいさなきみの おおきなて
別の標語も見てみましょう。ぱっと目につくのは先ほど紹介した体言止めですが、ここではほかに二つの技があります。
まずは「倒置法」。日本語の文は、主に「〇〇は××を△△する」という作りになっていますが、倒置法は「△△する、〇〇は××を」というように入れ替えが行われます。これも本来後ろにくるものが前に出てくることで、強調する効果があります。この標語では「よくみせて」とまず言うことで、読者に「何を?」と疑問を抱かせ、「大きな手」と答えを出すことで、より印象付けるようになっています。
そしてもう一つが「対句法」。対になる言葉を並べることで、イメージをはっきりさせる効果があります。ここでは「ちいさな」「おおきな」が対の言葉になっており、ちいさな「きみ」が、よく見えるように大きくたかだかと手をあげるシーンが鮮やかに見えてきますね。
そのほか短歌的技法
ここまで紹介してきたレトリックは、詩歌以外のジャンルでもよく使われているものです。一方、短歌ならではの形式の表現についても少しみていきましょう。
折句
『ム』チャするな 『ジ』カンにゆとり 『コ』コロのよゆう
短歌を作る際、「57577」以外のルールを設けることがあります。上の標語では、ある言葉を一文字ずつ句の頭に使用する「折句(おりく)」というルールが使われています。ここでは「ムジコ(無事故)」を一字ずつ読み込んだ折句となっています。
ただごと歌
自転車は よそ見の間も 進んでる
ごくごく当たり前の内容ですが、このようなありのままの状況をよんだ短歌を「ただごと歌」と呼ぶことがあります。ただごと歌の厳密な定義は難しいところですが、そのシンプルさゆえに作る難易度は非常に高いのも特徴です。このようになんでも歌になるようで、実は難しかったりするのも、短歌を作る面白さといえますね!
さいごに
ここで紹介した以外にも様々なレトリックや表現技法がありますし、それらは日常生活でもしばしば使われているものだったりします。気になった表現をよく見てみると、実はそこにレトリックが隠れているなんてことも。
レトリックに注目することで、言葉に親しみ、短歌を読み解くきっかけのひとつにしてみてください!