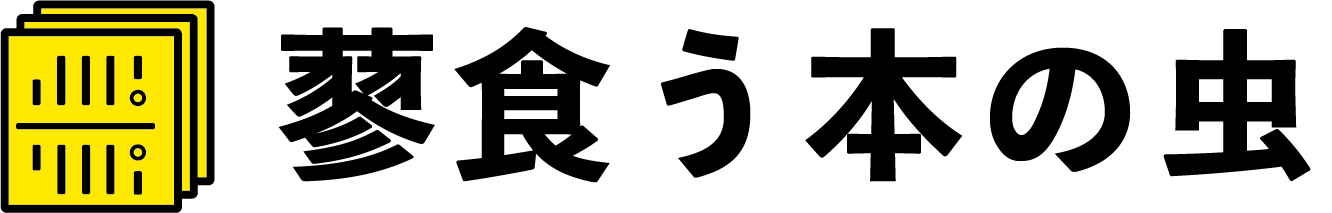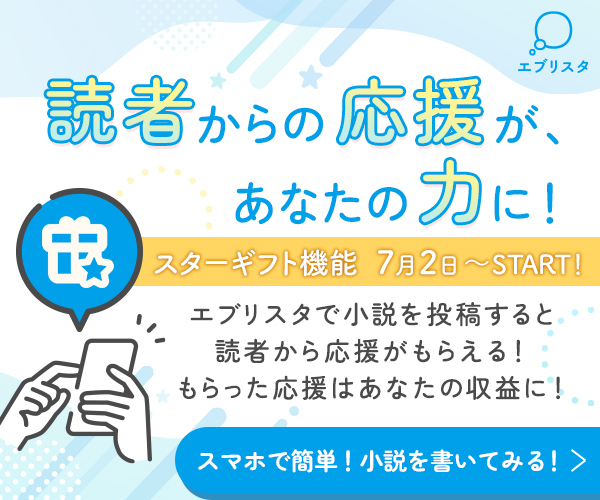これは独断と偏見なのですが、大学の文芸部・文芸サークルは、部会で集まったとしても特に文芸的な活動をするわけではありません。ぬるっと集まってわーっと喋ってぬるっと帰ります。
また、活動としても部誌を作るくらいで、取り立ててやることはありません。別に一人で小説を書いても大して変わらないのですが、同じような趣味の友だちと話せるから、まあそれはそれで良いのです。
そんな文芸部の活動として、何やら文芸部っぽいものが一つだけあります。それが「三題噺」です。
この記事の目次
三題噺とは
三題噺は、もともと落語の用語です。客席から3つのお題を出してもらい、それに基づいて即興で演じるというものでした。
落語といえば、古典的なものを話すイメージが強いかと思います。中には創作落語をする人もいますが、なかなか難しいもの。それなのに、三題噺はその場で与えられたお題で作るのですから、さらに難易度が上がります。
それを小説にも応用したのが、文芸部で行われている三題噺なのです。
いざ、小説版三題噺
というわけで、小説版の三題噺を紹介していきましょう!
……といっても、別に落語とやることは変わりません。何らかの方法でお題を3つ出し、各自がそのお題にそって書けば良いのです。
制限時間を1時間などと決めて即興で書くのも良いですが、ある程度時間をおいて、締め切りを設けるのが一般的だと思います。
お題の決め方は様々で、何人かでお題候補を書いた紙を袋に入れて引いても良いし、お題を出したい人が適当に3つ出しても良いと思います。
なお、診断メーカー上に「三題噺のお題メーカー」という便利なものがありますので、困ったらこちらを使ってみるのもおすすめ。
https://shindanmaker.com/58531
また、最近書けないなあと思っているときにやってみるのもおすすめ。スランプ気味のときって、何を書いたら良いのかわからない状況に陥っている場合が多いんですよね。しかし三題噺をやることで制限がかけられるので、とりあえず書き始めることができます。その中で、何か面白い発想に出会うことができるかもしれません。
制限をかけるだけであれば、お題は一つで良いかもしれません。ところが、異なるものを組み合わせることによって、思わぬ発見を生むことがあるのです。
俳句の世界に「二物衝撃」という言葉があります。これは、普通だったら一緒に使われないような言葉が組み合わさることで、新しい意味や詩情が生まれることを指し示します。
故に、お題の選び方はできるだけランダムな方が面白い作品を生み出せる可能性が高くなると思います。
書いた作品はどうする?
僕が文芸サークルに所属していた頃は、同じお題を使って書いた小説を集めて部誌に掲載したりしていました。部誌って別に特徴がないので大して読まれないのですが、三題噺だと「ここに載っている小説はすべて同じお題で書かれている」という引っかかりが作れるので、若干読まれやすくなります。
また、他の人の小説を読んで「このお題はこういう使い方をしてきたか〜!!」と盛り上がるのも楽しいものです。
個人で書いたものも、せっかくなら小説投稿サイトにあげてみるのも面白いと思います。
まとめ
文芸部の活動として何もやることがない! というときには、三題噺のことを思い出してみてください。
他にも、上で紹介した「即興小説」や、みんなで順番に小説を書いていく「リレー小説」なども活動としては面白いのですが、こちらはまたの機会に。