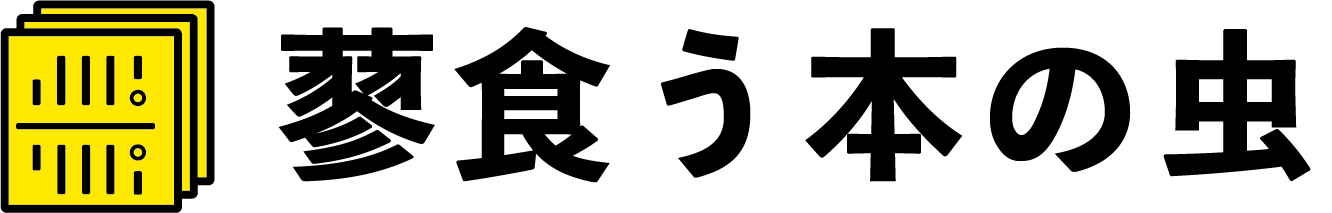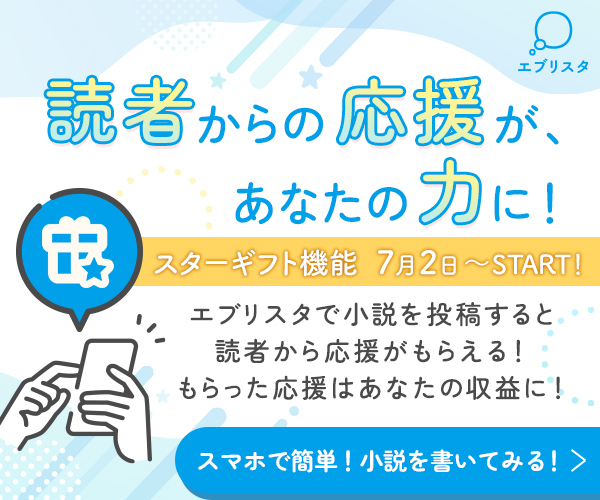「推理小説が上手く書けない」と悩んでいるあなた。はじめから「読者を騙せるような、巧妙なトリックを作ろう」と思っていませんか? 推理小説だからといって、他の分野の執筆と異なる意気込みや、守るべき執筆順序というものはありません。他の分野の小説のように、書きやすいように書けばいいのです。
この記事では、シャーロックホームズや横溝正史、中山七里を始めとする推理小説を愛読し、自身も推理小説を書く私がよく使う「先に世界観を作る推理小説の書き方」を紹介します。あなたの執筆活動の参考になれば幸いです。
トリックよりも先に世界観を作る
舞台や役者が整っていないのに、巧妙なトリックを決めるのは大変です。まずはキャラクターの設定やおおまかな話の流れを決めて、世界観を作っていきましょう。
基本情報の決め方
世界観を決める要素となる情報には、以下のようなものがあります。
- そのストーリーで題材にしたいテーマ
- 描きたい人物像・人生像(大まか)
- 舞台となる場所
- 人物の詳細
はじめにこれらを設定するのには、ざっくりとした物語の方向性を決める意味合いがあります。
推理小説のテーマといえば、パニック、愛憎、怨恨、ホラーなどをよく見かけますが、今回はテーマを怨恨に設定するとしましょう。するとトリックやなどストーリーの流れも限定されてきます。怨恨ならできるだけ苦痛・恐怖の伴う方法や、直接手を下す方向に流れやすいでしょうと思います。物語の大枠を作っておくことで、トリックの方向性を決めることにもなるのです。
ここで実際に、私がプロットを作る過程を紹介していきましょう。私は、テーマよりも先に人物の設定を決める場合がほとんどです。動かすキャラクターの方向性が決まっていれば、かなり物語を動かしやすくなります。
キャラクター作りでは「何を欲している人物か(何が欠けているのか)」から考えるのがおすすめです。そうすることで、比較的スムーズに作れますし人間味も出てきやすくなります。例えば、
A:人に認めてもらいたい、愛されたい
→必要とされる人間でなければいけないと思っている。相手の希望をくみ取ろうとする観察眼が鋭く、人のためによく動くキャラクター
→自己肯定感が低めで、いっぱいいっぱいの頑張り屋さん。人から信頼されたいと思っている。
B:仕事を成功させたい、安心できる収入が欲しい
→仕事の話をよく持ち出す、仕事の獲得に燃えるキャラクター
→将来を不安に思っていて、なんとか今のうちにしっかりした預貯金を作っておきたいと思っている。自分だけを信頼し、自力で道を開拓しようとしている。
C:仲間と楽しく日々を過ごしたい、孤独が嫌
→楽観的、仲裁役、リーダー / ムードメーカー的、よく首を突っ込むキャラクター
→日々の楽しさを追求するプラス思考の人。落ち込むことはあっても、あまり引きずらない。精神的な余裕も多く、あまり取り乱さない。信頼関係を深く築くタイプではなく、パートナーはとっかえひっかえする遊び人。
というように。もちろん同じテーマをもとにしてキャラクターを作っても、十人十色の人物像ができるでしょう。ここは、作家の個性の出しどころです。ここに探偵役のキャラクターを加えれば、登場人物が揃います。
次に「彼ら・彼女らが一堂に会するならどこがいいか?」「どういうテーマなら、全員が無理なく行動できるのか?」を決めていきます。
このメンバーであれば、温泉宿、カフェ、都内のビジネス街・ビルなど、どこでもテーマに合わせて舞台を設定できるでしょう。
これらのキャラクターに共通するのは「信頼」というワードでしょうか。そこでいったん、相手との信頼関係の構築が重要になる、恋愛にフォーカスしてみましょう。推理が絡むとなれば、恋愛に犯罪をからめて愛憎をテーマにしてみます。「壮絶な愛憎を伴う殺人に触れることで、キャラクター達は大きな影響を受けた」という大筋です。
舞台は、温泉宿にしてみます。
- 有名な温泉街のはずれ……相手を誘いやすく、かつ人気の少ない静かな場所
- マイナーな温泉地……誘うのが少々難しいものの、人気が無く自由に行動できる
です。キャラクターたちはまとまった休日を利用して温泉宿を訪れていたものの、そこで事件に巻き込まれてしまいます。
そして最後に、人物の詳細を決めていきましょう。人物の詳細と言っても、詳しいプロフィールをつくるわけではありません。
事件発生時や事情聴取時など、素の動きが出そうな場面に出くわした際にどういう行動を取っていそうか、自由にできる時間にどういう行動をしそうかという観点から決めていきます。
上述したA・B・Cの人物を元に、設定を膨らませていきます。
Aは突然の事件に挙動不審になってしまい、犯人に疑われる。しかし犯行時刻に売店でのアリバイ証言があり除外される。
Bは犯行時刻に取引先とウェブ会議をしており、アリバイが成立。せっかくだとコネクション作りをする中で、重要な情報を掴む。
Cは先日パートナーと別れたばかりで、気分転換がてらに旅行へ。チェックイン直後の事件発生のため被疑者から除外される。1のメンタルケアに一役買う。
このように、キャラを絡ませながら徐々に話を膨らませていきます。ここでストーリーの構成を考える必要はありません。物語の時系列に沿って、話を膨らませましょう。
話の山場・流れを決める
大体の世界観が作れたら、話の山場をどこに作るのかを決めていきます。ストーリーの展開方法を、以下のようなものから一つ決めておきましょう。
- 物語の後半に大きい山場を持ってきて、それまで徐々に高めていく
- 小さな山場を多く作って、最後に大きなものを一つ、ドンと持ってくる
- はじめに大きな山場を持ってくる
話の山場のパターンを決めておくと、どこでどの情報を出すべきかが決まってくるため、執筆が楽になります。
さらに、これを紙に書き出しておくと確認しやすく便利です。
トリックの作り方
トリックに関しては、その推理小説がどういうタイプのものかにも関係してきます。
そもそも推理小説とは、謎解きに重点が置かれている小説のことを言います。つまり、犯罪が絡まなくても謎解きがあるのであれば、それは推理小説です。カテゴリーとして
- 犯罪小説……謎の中心である犯罪に重点のある小説
- 探偵小説……誰が、どういう動機・方法によって行ったのか推理する
などがあります。共通事項として謎が当事者に与える影響に重点を置くもの、ということが挙げられます。
犯罪小説や探偵小説ではアリバイやトリックを避けては通れません。トリックは一から考えても良いですし、既存のトリックから着想を得ても良いでしょう。
オリジナルのトリックを考える場合には、シンプルな仕掛けをするのがおすすめです。高度な専門知識が必要とされるトリックにすると、解説をしても読者が置いてけぼりになってしまいます。それだけでなく、犯人も専門知識を有する人物に限定されてしまいます。
極端な例にはなりますが、被疑者をサラリーマン・薬剤師・専業主婦・中学生、被害者を薬局の常連という顔触れでトリックを決めようとします。そのトリックが「処方薬に微量の毒を混入させ続けてていた」だと、薬を包む薬剤師しか犯人になりえないですよね。
途中で「技術・知識的に、この人しか犯人になりえない、でも何故?」となるよりも、複数人候補に上がってしまえる、あるいは誰にもできっこないと思えるのになされた、巧妙なトリックの設定が重要です。
一方で既存のトリックから着想を得る場合、元のトリックに似過ぎないこと、すでにその小説を読んでいる読者に気が付かれないレベルまで進化させ、あくまでオマージュにすること、などが重要になってきます。
「トリックを拝借するのっていいの?」と思う方もいるでしょう。しかし、推理小説におけるオマージュというのは度々あります。例えば、アガサ・クリスティーの「そして誰もいなくなった」のオマージュ作品として以下の作品が挙げられます。
- そして誰かいなくなった 夏樹静子
- そして誰もいなくなる 今邑彩
- 十角館の殺人 綾辻行人
- ジェリーフィッシュは凍らない 市川景人
- そして五人がいなくなる名探偵夢水清志郎事件ノート はやみねかおる
推理小説が好きなあなたは、トリックにたくさんの種類があることを理解されていることでしょう。まっさらな何もない状態からそうしたトリックを生み出すのは、簡単なことではありません。
そこで、いままで読んできた推理小説のトリックがあなたの中に蓄積されているはずです。それらを組み合わせたり、アレンジしたりして独自のトリックを生み出すのも一つの選択肢と考えられます。
また、こうしたトリックを考える際には、事前に詳細を決めてしまうと執筆が楽です。「誰が」「いつ」「どこで」「誰と」「何をした」……いわゆる5W1Hまで設定を煮詰めておくと、設定ブレや矛盾が生じにくくなります。
そしてもちろん、この設定は後々必要があれば都度修正をしていきます。記録を取るように、詳細にキャラクターの行動を描き出しておきましょう。

こちらは私が実際に作った日程表です。不要な動きを消したり、書き終わった所には目印をつけたりしながら執筆を進めていきます。
執筆の道標となる資料の作り方
トリックやキャラクターの行動が決まったら、それを見返せるように資料として残しておきましょう。私は設定をWordで作成し、印刷したものに手書きで修正をしていきます。
設定の微調整
キャラクターの設定を見直し、最終的な資料の完成を目指します。キャラクターの性格と動きに矛盾はないか、日程に無理はないか、という点を主にチェックしましょう。
例えば、第1章で触れた「周囲をよく見て人のために動くキャラクター」が、仲間を見捨てて自分の興味のままに動いていたら、特別の事情がない限り違和感がありますよね。
そうした矛盾を見つけたのであれば、他のキャラクターにその役割を回したり、やむにやまれぬ事情を作ったりする必要があります。そうした描写をどこに入れ込むのかによって、場合によっては日程がずれこむこともあるでしょう。
これをほぼ書き上げた後に修正しようとすると、かなりの労力が必要になります。執筆前に確認しておくことで、安心して書き進められます。
次に、舞台となる場所が実際にあるのなら、その地理的な要素も絡めてチェックします。駅や人里から遠いのか、近いのか。ひとけはあるのか、すぐに助けを呼べる場所なのか、トリックは実行可能なものか、気候はどうかなどです。
「あくまで創作物なのに、そこまでする必要はあるのか」と思う方もいるでしょう。しかし、作品にリアリティをもたせるための無理のない設定・トリックや、リアリティのある情景描写のためには重要な作業です。
執筆に相当切羽詰まっていない限り、この作業はしておくのがおすすめです。
必要に応じて家系図・相関図などの作成
推理小説では、登場人物が2,3人で済むというのはなかなか無いと思います。少なくとも5,6人ほどは人物が出てくるはずです。そうしたキャラクターたちの関係性をあやふやにしてしまわないためにも、家系図や相関図などを作成しておくことをおすすめします。
例えば、家系にまつわる話、遺言にまつわる謎を探る話など、世代を超えて影響を及ぼすような伏線がある場合、その人物の生没年まで含めて家系図を作成しておくと便利です。

自分自身がわかればいいので、上記のように雑なもので大丈夫です。印刷した各種設定の裏面やメモなどに書いておきましょう。
私は、この作業をしている途中で設定に無理があることがわかり、1世代ぶん時間設定をずらす必要ができました。
始めはもう一世代少なく設定していたのですが、発端となる事件(1858年~1860年)に絡めるためには、主人公祐輔と助作までの間に3代分の時間が必要になることに気が付きました。そこであわてて書き直したのが、この写真の家系図です。
こうしたことで後々の説明や手直しで頭を悩ませないためにも、はじめに決めておくと安心です。
おわりに
今回は私の、推理小説のプロットの作り方を紹介させていただきました。
- まず世界観を始めにつくり、その次にトリックを決める
- キャラクターは「何を欲しているのか(欠けているのか)」を起点にすると作りやすい
- 必要なら家系図などを作成しておくと無理のある設定に気がつきやすい
などがポイントでした。もちろん、人それぞれの作成方法があるかと思います。
「どうやってプロットを作るのがいいのか」というものには、確固たる正解はありません。そんなに詳細を決めてしまってはキャラの動きが悪くなる、と思う方もいるでしょう。
あくまでも一例として、プロット作りに悩む方の参考になれば幸いです。