「青春小説」とは何か。最近、そういうことを考えます。
僕は、ずっと「青春小説」が好きだと思っていました。思春期にあたる中高生たちの揺れる気持ち、教室の風景、かわいらしい恋愛、などなど……。そういうものがぎゅっと詰まった「青春小説」が、大好きなのです。それは、高校を出て大学を出て、もう自分が生きている今を青春とは呼べなくなってしまった今でも。
僕は、自分の青春が不幸なものであったとは決して思いませんが、それでも「青春小説」に描かれている完璧な青春には敵わないなと思います。それを読んで、自分の青春時代と比べて打ちひしがれることが確実にわかっていても、僕は「青春小説」を読まずにはいられないのです。
青春小説とは何か
ところで、ふと一つの疑問がわき上がってきました。
「青春小説」とは何か?
「SF小説」や「ミステリ」というジャンルはあるし、そういうものの愛好家はたくさんいます。それは、各大学に「SF研究会」や「ミステリ研究会」などのサークルが多数あることが示していることです。


ところが、「青春小説」は…?

大学サークルのサイトがSEOに強いわけもなく、タイトルに「青春小説 研究会」というワードが入っていれば、Google検索の上の方に来るだろうということは容易に想像することができます。しかし、ここまでヒットしたサークル名に「青春」の文字はないのです。
ということは、恐らく大学のサークルとして「青春小説研究会」というものは存在しないのでしょう。また、検索結果に引っかからないところを見ると、大学サークルだけではなく、社会人の同人団体としてもそういうものは存在しないということなのでしょうか。
もしかして、「青春小説」という言葉がそれほど認知されているものではないのかもしれない。そう思ったのですが、一応Wikipediaのページはありました。
ここには、青春小説の定義が次のように書かれています。
青春小説(せいしゅんしょうせつ)とは、恋愛小説や、冒険小説のように小説全体(大きなまとまり)からある基準で小さく分類した小説のことをあらわし、その物語における主人公、または主人公を含めた登場人物が若年であり、内容がモラトリアムでしか体験できないこと、などある一定の基準を満たした小説のことを示す。登場人物の年齢やテーマからビルドゥングスロマンの体裁をとることも多い。
説明できているような、できていないような…。「ある一定の基準」とありますが、このページでこの基準がさらに明かされることもなく、結局今のところ僕らに残されている「青春小説」の定義情報は、
・その物語における主人公、または主人公を含めた登場人物が若年である
・内容がモラトリアムでしか体験できないこと
しかありません。僕が大好きだと思っていた「青春小説」という言葉の中に広がる世界は、これほど狭いものだったのです。
「青春小説」を対象にした文学賞
ただし、まだ希望を捨ててはいけません。Wikipediaによると、青春小説を対象として文学賞が二つあるとのこと。Wikipediaの情報を鵜呑みにするなと大学の授業で散々教えられてきましたが、参考にするのは自由です。
早速、確認してみましょう。
坊ちゃん文学賞

まず一つ目は、愛媛県松山市が主催の「坊ちゃん文学賞」。この賞の概要には次のように書かれています。
松山市は1889年(明治22年)の市制施行以来、四国の中核都市として発展を遂げる一方、文化的にも、正岡子規、高浜虚子など多くの俳人を輩出、夏目漱石の代表作『坊っちゃん』の舞台となった地として全国に知られています。
「坊っちゃん文学賞」は、このような文学的な背景のある本市が、新しい青春文学の創造を目指して1989年(平成元年)の市制100周年を機に創設したものです。
これは確かに、「青春小説」の賞であるということができそうです。募集要項のトップに掲げられている写真も、青と白を基調としていてどこかは儚く、そこに遠くを見つめている少女が配置されている。まさに「青春」という趣です。
今回で15回目の開催となる同賞ですが、第4回の受賞作である「がんばっていきまっしょい」は、連続ドラマとして放映されています。僕も子どもの頃、リアルタイムで見ていました。
しかも特筆すべきなのは、賞金は大賞200万円、佳作50万円であるということです。昨今、純文学系新人賞の賞金が50万円〜100万円であることを考えると、なんとも夢のある話です。
野生時代青春文学大賞
野生時代でも青春小説の賞が開催されている! と思ってわくわくしながら概要を覗きに行ったのですが、なんとこちらは2005年から2008年の4回のみで終わってしまっているようです。
もっと「青春小説」に真面目になりたい
繰り返すようですが、僕は「青春小説」が好きです。僕が読書に没頭するようになったきっかけを作ってくれたのは、森絵都の『カラフル』でした。その後、彼女の書いた「青春小説」以外の物語も読みましたが、やはり僕は、彼女の書いた「青春小説」が僕は特に大好きです。『アーモンド入りチョコレートのワルツ』『つきのふね』『永遠の出口』などなど。
その後も、佐藤多佳子の『黄色い目の魚』、綿矢りさの『インストール』『蹴りたい背中』、森見登美彦の『夜は短し歩けよ乙女』など、中学生〜大学生の青春を描いた様々な「青春小説」を読んで育ってきました。
しかし、「青春小説」とは何か? その問いに、僕は明確に答えることができません。そこに議論を生み出すことすらできません。ひとまず「青春小説」を主人公や登場人物が中学生〜高校生の人物の小説であるとして、それに関する議論をもっと深めたいなと僕は思うわけです。
そして、その中心となるような「場」を作り出したい。もちろん、僕も青春小説に対して様々なことを考えていきたいと思いますが、他の方の論考も応援したい。そのような気持ちから、蓼食う本の虫では、今後「青春小説」に関する記事のご寄稿を歓迎したいと思います。そしてそれらの記事を、「青春小説研究会」という一つのカテゴリに束ねたいと思います。
記事の寄稿に関していは、以下のページを参考にしてください。
「青春小説」の素朴な感想文や書評から、「青春小説」や「青春」という言葉を巡る議論、あるいは現代の「青春小説」の中で何が起こっているのか、ということについて、広く記事のご寄稿を受け付けたいと思っております。
ぜひ「青春小説」に対して強い思い入れのあるという方は、ご応募いただけますと幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
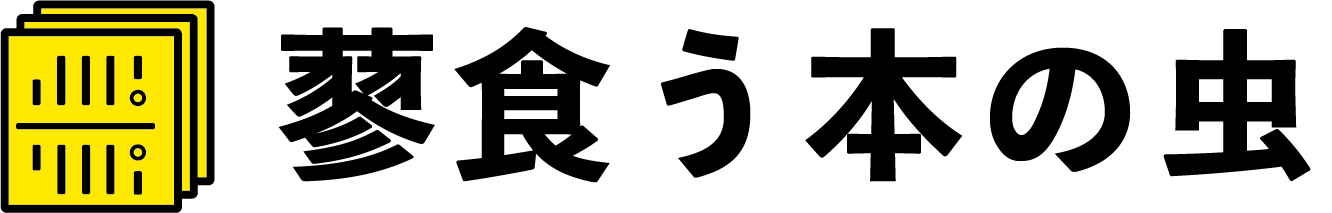
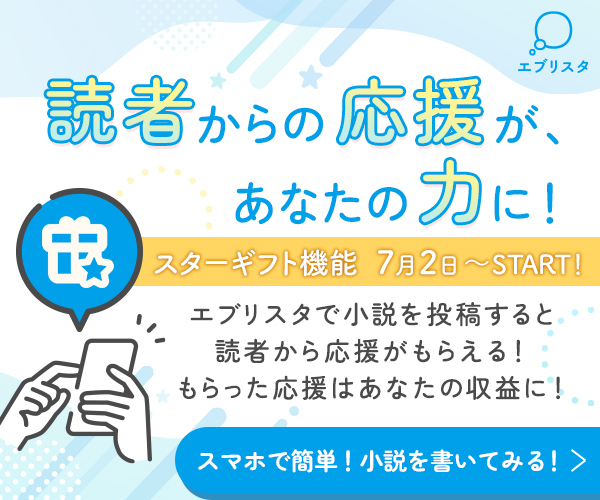





コメントを残す